音楽資料目録のヒント:テーマ 16:楽曲のタイプ
「音楽作品の典拠形アクセス・ポイントで使用する楽曲のタイプ」
当社ホームページで pdf ファイルを公開中です (DL可能).
https://toccata.co.jp/about-us/
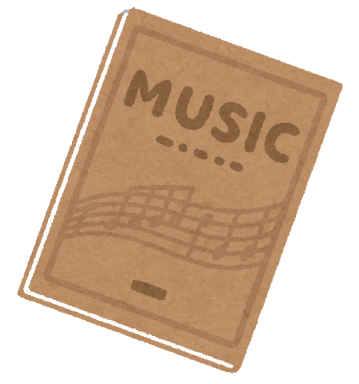
このリストは,
「音楽資料目録作成マニュアル. Part 2, 音楽作品の総称的タイトル一覧」 (1997) の改訂版です.
[楽曲のタイプとは]
このリストでは “Type of composition” を
「楽曲のタイプ」 「楽曲タイプ」と表記しています.
日本目録規則2018年版で使われている 「楽曲形式の名称」 を採用しなかった理由は,
楽曲形式 (=音楽形式: Concerto, Sonata, Symphony 等) の他に
速度標語 (Adagio, Allegro 等)
楽器や声の組合せ (Duet, Trio,Quartet 等)
多くの作曲者が使用している一般用語 (Music, Piece 等)
ラテン語の典礼的タイトル(Gloria, Salve Regina, Te Deum 等) も含まれ,
楽曲形式に限定されないためです.
RDA 用語集では
→ 楽曲のタイプ (type of composition) とは
「さまざまな作曲家によって頻繁に使用される,形式,ジャンル,または一般的な用語 [例: Capriccio, Concerto, Magnificat, Mass, Movement等]」
→ 個別的タイトル (distinctive title)」 とは
「形式や音楽ジャンル,速度標語,演奏者数,または典礼文の種類のみではないタイトル」
と定義しています.
[総称的なタイプか,個別的か]
RDA を使用して目録作業を行う音楽カタロガーにとって,
音楽作品を表すアクセス・ポイントを構築する際に
何が 「音楽作品のタイプ」 の名称か,という問題は重要です.
優先タイトルが
総称的なタイプの名称であるか
個別的タイトルであるかによって,
典拠形アクセス・ポイントを構築する際の RDA の指示が異なってきます(RDA 6.28.1.9,6.28.1.10).
総称的/個別的の区別は,
→ 優先タイトルで使用する言語の選択 (RDA 6.14.2.5.2.1)
→ 本タイトルを記録するときにどの要素を含めるか (RDA 2.3.2.8.1)
にも影響します.
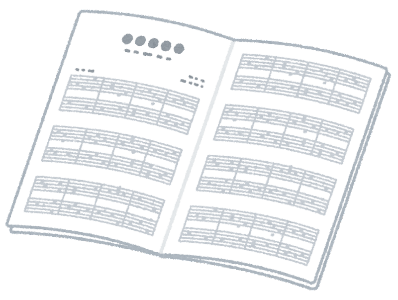
RDA 6.14.2.5.2.1 では,
楽曲タイプの名称が 目録作成機関の定めた優先言語に同根語 (共通の起源を持つ単語) があるか,
または同じ名称がその言語において使用されている場合に
その容認された形を記録するよう指示しています.
英語を採用する目録作成機関では
その名称に英語の同根語があれば,
作曲者がどのように綴ったかにかかわらず英語の用語が使用されます.
例として Symphonie, Sinfonie, Sinfonia ではなく 「Symphony」 を使用します.
このように,カタロガーはどの言語を使用するかを判断するために
その用語が一般的なタイプかどうかを知る必要があります.
このリストは
どの用語がタイプ名とみなされ,どの用語を個別的とみなすかを決定する際の一助となります.
英語の同根語がない楽曲タイプの名称では
作曲家が元々使用していた言語を確認し,
作曲家がそのタイプの楽曲を複数書いていることが知られている場合には
その言語の「複数形」を使用する必要があります.
このリストは,それぞれの言語でのタイトルの複数形を知るための
レファレンス・ソースとしても利用できます.
AACR2 時代から現在に至るまで
Toccata では,規則に則りメタデータを構築してきました.
一貫した取り組みによる蓄積がございます.
さまざまな機関で,所蔵数が大きくなるにつれ
機能的なメタデータの構築が望まれています.
音楽資料の 《発見可能性》 を高めるため,Toccata MARC をご活用ください.
[参考文献]
鳥海恵司 (2024).音楽作品の典拠形アクセス・ポイントで使用する楽曲のタイプ.株式会社トッカータ
https://toccata.co.jp/wp-content/uploads/2024/09/Types-of-composition.pdf
2025年8月4日付 図書館情報部より全国送信mail[CDご選定用データ,最新情報]より
一部加工修正しました
